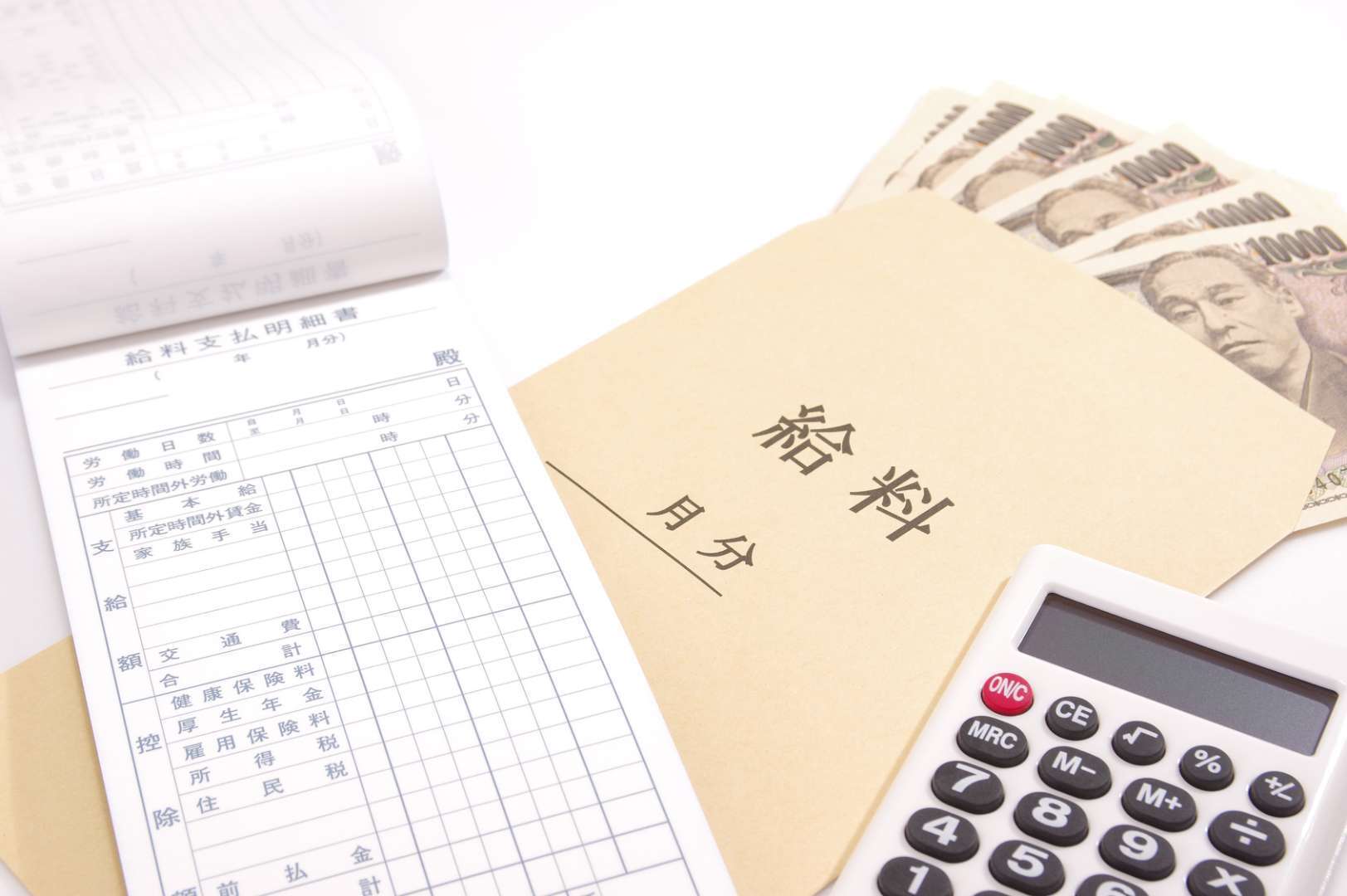「設備屋って、あんまり稼げない仕事なんでしょ?」そんな声を耳にすることがあります。実際、建設業の中でも設備工事は地味な印象を持たれがちで、年収についても過小評価されている側面があります。しかし、そのイメージは本当に現実と一致しているのでしょうか。
たしかに、経験の浅い若手や、資格を持たない職人の場合、初任給や20代の年収は決して高くありません。地域差も大きく、小規模事業者が多い業界構造も影響しているかもしれません。ただ、それだけで「稼げない」と断じてしまうのは早計です。
なぜなら、設備業の中にも安定して収入を得ている人は多くいますし、年齢や役割によって収入の幅が大きく変わる世界でもあります。特に現場をまとめる立場や、資格を活かして施工管理を行うポジションでは、年収600万円以上の事例も珍しくありません。
この記事では、「設備屋=低年収」というイメージの真偽を、できるかぎり冷静に整理しながら、どんな働き方をすれば収入を伸ばせるのかを探っていきます。
設備業の年収、平均いくら?年齢・職種・地域別に読み解く
設備屋として働く人の年収は、実は「一律」では語れません。年齢や職種、地域によって大きく異なります。たとえば20代前半で未経験から始めた場合、年収は250万〜300万円台が一般的です。これは他業種と比べても決して高くはない水準です。しかし、30代で現場経験を積み、資格を取得し、安定した会社に勤めていれば、年収400万〜500万円に達することも珍しくありません。
職種による差も無視できません。給排水や衛生設備などの工事に携わる「現場作業員」と、工程管理や元請との折衝も担う「施工管理職」では求められるスキルが異なるため、後者のほうが給与水準は高めです。さらに、空調・冷暖房・換気など専門性が高い分野を扱う職種では、特定の資格(冷凍機械責任者や電気工事士など)を有することで、収入アップが期待できます。
地域による違いも大きく、首都圏や都市部は工事単価や人件費が高めに設定されているため、同じ職種でも地方に比べて年収が1〜2割上回る傾向があります。ただし、その分生活費もかかるため、実質的な可処分所得で見ると一概には比較できません。
このように、設備屋の年収は「安い」と一括りにするにはあまりに多様です。自分がどの地域で、どんな職種で、どのくらいの経験を持ち、どんな会社に属しているかによって、大きく変わってきます。重要なのは「今の年収が業界平均と比べてどの位置にあるのか」を客観的に把握することです。
同じ仕事でなぜ差が?年収に差が出る3つの要因
「同じ設備屋なのに、なぜあの人はそんなに稼いでいるんだろう?」現場でよく聞く疑問です。年収の差は、単に年齢や勤続年数だけでなく、いくつかの要素が複雑に絡み合って生まれます。そのなかでも特に大きな影響を与えるのが、①資格の有無、②業務範囲の広さ、③会社の規模と方針です。
まず1つ目の「資格の有無」はわかりやすい要素です。たとえば、2級管工事施工管理技士を持っているだけでも、現場の責任者として配置されることが可能になり、基本給や手当が上乗せされます。1級資格を取得すれば、より大規模な現場や公共工事などを任されることもあり、年収の水準は一段と上がります。逆に無資格だと、補助作業にとどまるケースが多く、収入にも限界があります。
2つ目は「業務範囲の広さ」。配管工一筋よりも、空調・給排水・衛生など複数の分野を対応できる人は、現場でも重宝されます。また、材料発注や工程調整、安全管理といった「管理業務」まで担えると、現場を動かす立場になり、報酬も変わってきます。手を動かすだけでなく、考えて動ける力が評価される場面は確実に増えています。
3つ目は「会社の規模と方針」。福利厚生が整っている会社では、基本給がやや低くても賞与や手当、昇給制度でカバーされることが多いです。逆に、業績や評価が報酬に直結する成果主義の会社では、働き方次第で大きく年収を伸ばすことも可能です。
こうした違いを理解していないと、「自分の給料はこんなもの」と思い込んでしまいます。年収を上げるには、まずその構造を知ることが第一歩です。
年収を上げたい設備屋がまずやるべきことは?
「もっと稼ぎたい」と思ったとき、何から手をつければいいか。設備屋の仕事では、年収アップにつながる道筋がいくつかありますが、最初に考えるべきは「資格」と「現場での役割の広げ方」です。
まず、資格の取得は最も確実なステップです。現場作業を続けながら、2級管工事施工管理技士や電気工事士などを取得することで、施工管理補助や現場主任のポジションを任されるチャンスが生まれます。現場では有資格者の配置が法令で求められる場面も多く、資格を持っているだけで手当が付く会社も少なくありません。さらに経験を積んで1級を取得できれば、公共工事や大規模案件も視野に入り、年収はさらに安定・上昇しやすくなります。
次に大切なのは、自分の担当範囲を広げる意識です。「指示された作業だけ」から一歩進んで、資材の準備や工程の段取り、安全確認まで関われるようになると、現場での信頼も変わってきます。管理的な視点を持つことで、会社からの評価も大きくなり、昇給やポジションアップにつながります。
加えて、社内外との「やりとり」に強くなることも重要です。職人仕事に集中するあまり、元請や施主とのコミュニケーションを苦手とする人もいますが、対話ができる現場担当者は重宝されます。特に、言葉遣いや段取りの説明がきちんとできる人は、仕事の任され方が違ってきます。
年収を上げるには、劇的な変化を求めるのではなく、地道な積み重ねが近道です。「技術力」「管理力」「対話力」、この3つを意識して育てていくことで、収入と評価は自然とついてきます。
今の職場で限界を感じたら?転職市場での評価と注意点
どれだけ努力をしても、今の職場では年収が頭打ち…そんな状況に直面したとき、転職という選択肢が現実味を帯びてきます。設備業界においても、一定の経験や資格を持つ人材は他社からの需要が高く、適切な環境に移ることで収入や待遇が改善されることも少なくありません。
特に評価されやすいのは、2級以上の施工管理技士を保有している人や、空調・給排水・衛生といった複数の工種を経験している人です。現場だけでなく工程や安全、品質の管理まで関わった実績がある人は、施工管理職としての需要が高く、年収500万円以上の求人が比較的安定して存在します。
ただし、転職には注意すべき点もあります。たとえば、給与額だけで判断してしまうと、労働時間が極端に長かったり、現場のサポート体制が整っていなかったりと、働きにくさに悩むケースもあります。年収が高い=自分に合っている、とは限らないのが現実です。
また、資格やスキルを持っていても、それを現場でどう活かしてきたか、どんな責任を担ってきたかを具体的に語れる人は意外と少ないものです。書類や面接では「自分の強みを伝える力」も問われます。自分のこれまでの実績を整理しておくことが、良い職場と出会うための準備になります。
転職は、今の会社から逃げる手段ではなく、より納得できる働き方を選び直す行動です。今の環境で挑戦できることをやり切ったうえで、視野を広げるのは前向きな選択です。
もし、もっと成長できる環境を探したいと感じた方は、こちらのページも参考になるかもしれません。
https://www.kashiwa-setsubi.net/recruit
設備屋の年収は、自分次第で確実に変えられる
「設備屋=稼げない」というイメージは、一部の事実を切り取った誤解に過ぎません。実際には、資格を取り、現場での役割を広げ、管理や調整の力を磨くことで、年収を着実に上げている人も多く存在します。重要なのは、自分の立ち位置を正しく把握し、どこに努力の軸を置くかを見極めることです。
環境に恵まれていないと感じるなら、転職という選択肢もありますし、今の会社で新しい役割に挑戦する道もあります。変化を起こすかどうかは、自分自身の意志に委ねられています。
焦らず、しかし確実に。年収を上げる道は、決して派手ではなくても、着実に積み重ねていけるものです。自分に合った働き方や成長の方向性を見つけるきっかけになれば幸いです。
もし現在の環境や将来像について少しでも考えることがあれば、こちらもあわせてご覧ください。